|
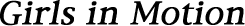
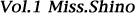


TEXT/YUJI UEDA
その頃はまだ、ただの「ヘンな宗教の連中」って呼んでいたらしい。
上九一色村の第7サティアンはマスコミが騒ぎ出す何年も前から、
地元のヒマな若い連中の深夜のあてどないドライブの行き先として、人気のスポットだった。
「高校出たばかりの頃、土曜日の夜中。仲間が集まるととりあえず行ってみようかってことになって、
よくクルマで見に行った。入り口のゲートに監視小屋みたいなのがあって、
宇宙服みたいなのを着た人が中にいて、仲間の男のコがヤジ飛ばしてからかったり
……一度、爆竹投げ込んだヤツがいて、その時はうぉおおおおーって激怒りになってクルマで追いかけてきた」
濃い霧が立ちこめる真夜中の国道139号線。
竹ヤリ仕様のスカイラインの助手席から恐る恐る覗いたドアミラーの中には、
すぐ後ろのカローラのハンドルを握る、発狂したゴリラみたいなオウム信者の顔があった
――。
静岡県沼津市に生まれて、そしてそこで育って、
完全自殺マニュアルがベストセラーになった年に二十歳になった、シノ。
「樹海を探検しに行ったりしてたのもちょうどその頃。だいたい友達に一人はそういうの好きな男のコがいて。
氷穴の土産物屋さんの駐車場にクルマを駐めて、遊歩道に沿って歩いてくと自殺防止の看板が立ってる。
その看板のわきの辺に必ず誰かが張ったビニールのテープが森の奥のほうに延びてるから、
いつもそれを伝って入っていく」そのテープは、彼ら同様不埒な見学者の仕業なのか、
遺体捜索に訪れた警察が残したものなのか、それとも自殺者本人が道しるべにしたものなのかは分からない。
そんなことはおかまいなしに彼らは、頭の中に鳴っている川口浩探検隊のテーマに合わせ、歩いていった。
溶岩流が固まった穴ボコだらけの大地は絶対にまっすぐには進めず、
360度同じ景色が続くなかで次第に方向感覚が麻痺していく。
最初一本だったテープは15分も歩けば枝分かれして、さらに進むとそれがまた3本に分かれていたりした。
「これじゃ帰るとき、どっちから来たか絶対分からなくなるよ」って誰かが言うが
「人数がいるから調子こいて」いちばんヤバそうなのを選んでまたずっと歩いていった。
一度だけ、ボロボロのテープに沿って、ずっとずっとずっと森の奥へ歩いていったことがあった。
それは黄色いテープだったのか、青だったのか赤だったのか……もう完全に色というものが抜け落ちた、
艶の無い灰色みたいな古びたテープだった。昔テレビで観た、
液体窒素に浸した植物の葉のようにパリパリとくずれてしまいそうな、頼りない命綱。
漠然とした恐怖が「絶対にこの先で誰かが死んでいる」という確信に変わった頃、
突然のように夕暮れがやってくる。半ばパニック状態で、必死で帰り道を探し回り、
彼女は数時間かかってようやく、もとの遊歩道に辿り着いた。
もうすっかり暗くなった森の中をほぼ半泣きで、とぼとぼと歩いて下っていったその日のことを今でも時々、
何かつらいことがあるとシノは思い出すんだという。
青木ヶ原樹海――。広さ約25万平方キロメーターのこの木々の海の中で、
今年も60人以上の自殺者の死体が発見された。
撮影場所のすぐ先の木陰にも、ここで最後の夜を過ごしたらしき人々の焚き火の跡や、
飲み散らかしたビールの空き缶や、脱ぎ捨てた着衣やカバンが放置された場所があった。
「本気で死ぬつもりの人は、最後、着ている服を全部燃やして、
全裸で森の奥に消えるんだっていつか友達から聞いたことがある」
駐車場わきの売店で買ったソフトクリームをなめながら、シノはさっきそう話した。
ピクニックに向かう家族連れで賑わう、ありふれた観光地みたいな樹海の入り口で。
雲の切れ間から夏の太陽が照りつけていた。
生き物の気配が全くしない、奇妙な静寂につつまれた死者たちの森に、ほんのかすかだが、
風が流れていく。 木々のざわめきが渦を巻き、僕らをどこかへ連れ去ろうとしている。

|