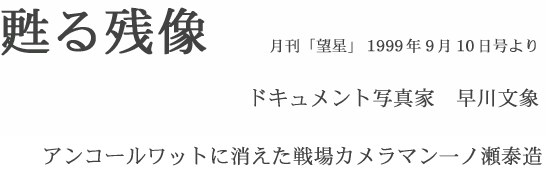いまから二十六年前、戦乱のインドシナで報道写真を撮りながら、解放戦線支配下にあったアンコールワットに潜入し、行方不明になった青年がいた。一ノ瀬泰造。ある程度年配の人なら『地雷を踏んだらサヨウナラ』の書名とともに彼の名を覚えている向きも多いだろう。その一ノ瀬泰造が、四半世紀のときを経て再び甦ろうとしている。写真展が開かれ、書簡集が再版され、年末にはその人生をドラマ化した映画も封切られる。現代の若者にも共感を呼びつつあるという一ノ瀬の生き方の、いったい何が人々を惹きつけるのか。また、彼と同時代の青春を生きた周囲の人々は、中年となった現在、どんな思いで当時といまを振り返るのか。一ノ瀬泰造の存在が「人生の道」を決めたという気鋭の写真家が、ブームの底流を探る。
四半世紀後のブーム
七月一日、九州・福岡。博多祇園山笠の祭り気分が高まりつつあるなか、ひとつの写真展が始まった。この春、中洲近くに完成したばかりの福岡アジア美術館。その会場に集まった報道陣や写真展関係者に混じって、ステッキを突いて立つ老夫婦の姿があった。やがて、その夫婦らのテープカットによって写真展の幕が開く。「一ノ瀬泰造写真展」。その老夫婦こそ写真家一ノ瀬泰造の両親であった。一ノ瀬泰造。フリーの報道カメラマンとして戦乱のインドシナに赴き、戦争写真を撮りながらクメールルージュ(カンボジア民族統一戦線)の占領下にあったアンコールワットへ潜入、行方不明となった男。わずか二年足らずの取材期間に撮影した写真は、消息を断って後、運よく約二万コマが両親の元に返って来た。それから四半世紀が過ぎたいま、戦火のベトナム、カンボジアで一ノ瀬が見た“瞬間”が122枚の写真となり、見る者の心に深く刻み込まれている。
写真展を前に、出版界では、絶版となっていた一ノ瀬の写真と戦場から友人や両親などに宛てた手紙類の書簡集『地雷を踏んだらサヨウナラ』が、文庫版で再版された。人気ライターによる伝記も企画された。また、書簡集と同名の映画が完成し、年末には封切りになる予定である。
一ノ瀬がアンコールワットに消えた一九七三年当時、彼は二十六歳を迎えたばかりだった。それから一ノ瀬が生きた人生と同じだけの時間が流れ、いままた、一ノ瀬は多くの人の心の中に現れた。まるで一ノ瀬泰造という強烈な個性が、その残像を実像として甦らせたかのように・・・。
私が一ノ瀬泰造を知ったのは八一年、高校二年のとき。一ノ瀬の両親や友人達が自費製作した写真集『遥かなりわがアンコールワット』の発刊を知らせる小さな記事を雑誌で読み、一ノ瀬の郷里・佐賀県武雄市から郵送してもらったのが最初だった。小包から現れたハードカバーの写真集。インクの匂いと真新しい光沢を放つ表紙には、アンコールワットの小さな写真があった。
緑鮮やかな密林の向こう、青空をバックにしたアンコールワットの中央塔が頭を見せている。表題の下には、被弾したカメラが重々しい雰囲気で大写しに印刷されていた。
銃弾が貫通し、信じられぬほどに変型したカメラ。それは高校生の私にとって何よりも衝撃的だった。裏表紙には同じカメラの反対側が写った真。TAIZOの文字と、その下方にあるセルフタイマーのレバーは一部が歪み、弾丸が入り込んだ痕が意外にも小さく、しかしはっきりとわかる。ベトナムのスアンロク近くで行われた作戦に従軍したとき持っていたカメラである。一ノ瀬は、戦闘が中断したとき、水汲みにきた北側の兵士を見つけて身を乗り出した。そのとたんに銃撃され、手にしていたカメラが吹き飛ばされた。一歩間違えばカメラだけでなくカメラを持った腕ごと吹き飛ばされていただろう。悪くすれば、一貫の終わりだった。だが、一ノ瀬は右手を負傷したもののたいしたことはなく、その後も一年以上にわたる取材を続けた。
何ということだ。それほどまでした写真を撮らねばならないのか。しかもそれは、会社や上司の命令でではなく、フリーの立場で、自分の意志に基づいた仕事としてである。世間を知らず、まだ幼かった当時の私は、一ノ瀬の姿を想像して、その生き方にシビれた。そして、生命を賭けてまでも撮らなければならない「写真」という存在に魅力を感じたものだった。
「フリーカメラマン」「写真」、一ノ瀬泰造はこの二つを私に強く印象づけてくれた。“優しさ”がでている写真
福岡での写真展には初日から一週間を待たずして二千人を超える観客が足を運んだ。いま、人々が一ノ瀬の写真のなかに見るものは何だろう。単にインドシナでの戦争を伝えるだけではない、われわれの意識の深いところで人間の営みを考えさせるような写真、戦う兵士だけでなく、むしろ戦地に暮らす民衆に向けたまなざし、戦時とは思えぬほどの子どもたちの明るい笑顔。一方で、どこから撃たれるかもわからない銃弾をものともせず、捨身の体当たりで撮った戦闘写真の凄さ。たとえば、ロケット砲弾の攻撃を受けて身を隠そうとする兵士たちの姿をとらえた写真。危険を感じ、自分も兵士たちと同じように身を伏せてしまうなら決して撮ることのできないシーンである。撮影している一ノ瀬の状況を想像するだけで背筋が冷たくなる。
<好きな仕事に命を賭けるシアワセな息子が死んでも悲しむことないヨ、母さん>
一ノ瀬泰造がカンボジアに入って間もなく故郷の母に宛てて書いた手紙のなかのことばが、写真展の導入部に掲げられていた。「俺は絶対に弾には当たらない」と言っていたというが、戦場で仕事をする以上は、やはり心のどこかで死を意識していたのだろう。それに、異国の地の、しかも戦場だったからこそ母を想う気持ちや母に対する優しさが膨らんだのではないか。危険な仕事に挑む息子の身を案ずる母親を安心させようとする純粋な心−この辺りに一ノ瀬泰造の魅力のひとつが現れているように思える。
今回の写真展に関する写真のプリントを担当した橋本文夫は、写真を焼くにあたり、現在残っている一ノ瀬のネガすべてに目を通した。プリントにした写真の前後に何が写っているか、一本のフィルムをどういう動きで撮影していたのかを二年近くに及ぶ作業のなかで見てきた。
「やっぱりな、というのが実感です。戦場で撮った写真でありながら優しさが出ている。カメラの位置を低くして、民衆の中で民衆と同じようなところで撮っているんです。きっと、カメラを写す道具ではなく語りかける道具として使ったのではないかな」
橋本は一ノ瀬の優しさを写真に認める。一ノ瀬とほぼ同世代の橋本は、航空撮影や建築写真を手掛ける写真家だ。学生時代から絵画を志していたが、職業としては成り立ちにくいため画をあきらめ写真を始めたという。写真館を経営していた父親の影響もあった。独学で暗室作業を覚えプリンターとしても活躍する。福岡での一ノ瀬泰造写真展を企画した一人でもある。
「以前から一ノ瀬さんの両親が息子の残したネガを自分達で焼いているのを知っていました。年をとっての暗室作業は大変だから、なんとかしてあげられないかなと思っていたんです」
同じ九州の中で作品を残しておきたい作家が一ノ瀬泰造でもあった。両親が元気なうちに自分のプリントで写真家一ノ瀬泰造の作品を残したいという気持ちから写真展は動き出した。
「いま、もし一ノ瀬さんが写真を撮っているとすれば、ファッション写真の大家になってるんじゃないかな。二十六年経っても古くないし、センスの良い写真だなと思います」同世代カメラマンの“思い”
一ノ瀬が行方不明になった翌年の七四年、報道カメラマンの浅田恒穂は初めてベトナムへ渡った。浅田は一ノ瀬よりも二歳若い。初めてベトナムの土を踏んだのは浅田も一ノ瀬も二十四のときである。ベトナムにいる友人から「助けにきてくれ」という手紙が届いたのがきっかけだった。カメラマンとして歩きだしていた浅田は、悲惨なベトナムを撮ろうと乗り込んでいく。が、ひところのベトナム報道が華やかだった時期とは状況が違っていた。アメリカが軍事的にベトナムから撤退したことで戦場写真の意味が変わってきていた。兵士たちにも厭戦気分が広がっていたのか、南ベトナム政府軍の規律は乱れ、万一のときの救援体制もなくなっていたと浅田は回想する。先輩カメラマンからはベトナムに来るのが「遅すぎるし早すぎる」と言われたそうだ。
アメリカ中心の商業ジャーナリズムは、もはや、命がけで撮った写真であっても、それに見合った価値を認めなくなっていたということだろう。
浅田は、翌七五年四月に再びベトナムに立った。解放軍が無血入城しサイゴンが陥落する直前のことである。同じころ、一ノ瀬がサイゴンに現れたというニュースが日本に伝えられた。ベトナム人カメラマンとの再会を喜んで抱き合っていた浅田を見間違えたUPIスタッフの話が誤報されたのだったが、確かに私が会った浅田氏の顔立ちはどことなく一ノ瀬に似ていた。
そんな縁もあってか、後に浅田は一ノ瀬の書簡集と写真集の出版にかかわることになる。当時のフリーカメラマンの集団「エヴァプレス インターナショナル」のメンバーの、同世代の同業者一ノ瀬が残した写真をなんとかしてやりたいという思いと、
息子のためにと思う両親の同じような気持ちが最初の書簡集に結集する。
「サイゴンから戻った一ノ瀬のネガを一週間かかって二千枚くらい焼いたんだけど、写真に写っているものが、戦場の血ではなく泥だったという印象が強かった。プリントを洗う水槽から泥が流れだすんじゃないかと錯覚するくらい強烈だった」
写真集の話では経費がかかりすぎるといって乗り気でなかった出版者も、個性的な一ノ瀬の手紙類をとり入れることで出版に踏み切った。出版にあわせた写真展も企画し、大盛況を収めた。
「写真としては決して上手いというのではないが、一ノ瀬という人間そのもの、彼自信が表現されている。青春を突っ走ったひとりの若者が映っている、そんな写真です」
浅田とともに一ノ瀬の写真集にかかわった楠山忠之は戦前生まれで、歳は一ノ瀬よりも上だが、新聞社のスタッフをしていたためフリーとしてのスタートは一ノ瀬と何年も違わなかった。そして浅田と同様、直接一ノ瀬とは接触していないにもかかわらず、写真集の編集を引き受けた。インドシナに関してはサイゴン陥落の前後四十日のベトナムを取材しただけの楠山にとって、一ノ瀬は自分のやり残した部分をカバーしてくれる存在に思えていたという。
「息子の写真を世に出そうと一生懸命になっている両親の姿に頭が下がったこともありますが、戦争の混乱に落とし込まれた人々のなかでシャッターを切った一ノ瀬君の写真が自分たちの言いたいことを代弁しているようで、わが事のように取り組んでいました」
自分の夢に向かって青春を駆け抜けた一ノ瀬泰造。二十年前の写真展では、わざわざアジアに出かけて行って命落として何がエライのか、といった批判もあったというが、いままた脚光を浴びているのは、若さに任せ、身体でものを考えたその姿に魅力があるからではないかと楠山は見る。
自分のために何かを求め、何かのために自分をぶつけていく。いまも昔も変わらない青春の本質が、一ノ瀬の生き方に見えている。
一ノ瀬泰造は、なぜ危険を承知でアンコールワットを目指したのか。日本ではこの四半世紀、多くのことが語られたが、友人たちはその謎を謎として抱えたまま、歳を重ねていった。そんな彼らの、脳裏に生きる若いままの一ノ瀬と、中年となった自分との「絆」とは何なのだろう。
冗談めかした友人への手紙
一ノ瀬泰造はなぜアンコールワットを目指したのだろう。
<アンコールにクメール・ルージュ、村人を撮ったら死んでもいいくらい、魅せられてしまったからです>
大学の恩師に宛てた手紙にはそう書かれていた。プノンペンに着いて間もないころ、
「行くこと自体が自殺行為だ」「捕まれば爪をはがされ、皮をむしられる」と周りの記者にたしなめられたが、それでもなお一ノ瀬はアンコールワットを目指す。当時、共産側の「解放区」にあり、状況のまったくわからなかったアンコールワット。
カンボジアに入って二ヶ月余りが過ぎた1972年5月、共産側にあったバライ湖畔の寺王産側から政府軍が奪還し、アンコールワット奪回も時間の問題との噂が流れはじめたころ。一ノ瀬はアンコールワットへあと1.5キロのところまで行く。そして、その付近にいた部隊の兵士に案内されて、破壊された遺跡などを撮影。しかし、その後の従軍を許されず、指令部まで連れ戻され、軍事機密を撮ったとの理由から、フィルムを没収されてしまった。司令官は二ヶ月後に返すといったが、再三の要求も叶わずフィルムはとうとう返ってこなかった。その後、それ以上アンコールわっとへ近づくこともできなかった。
そこが戦場である以上、死の危険は避けられない。だとしても、死あるいは帰れないことがわかっていながらアンコールへの潜入を決行するほど無謀だったとは考えられない。事実、一ノ瀬がアンコールへ向かう直前に友人や知人に宛てた手紙にも「危険はそう何回もせずサッとあきらめて」と記されている。しかしまた、同じ手紙の中には「地雷を踏んだらサヨウナラ」と、
冗談とも本気ともつかない文句を書いている。
そんな内容の手紙が73年11月も終わろうとするころ、友人・赤津孝夫の元へ届いた。
赤津と一ノ瀬は日大写真学科の同期で、二人ともフォトポエムという写真クラブに所属していた。下宿先が偶然にも近く、また、お互い職業軍人だった父親の教育を受けたという境遇もあって、二人は親交を深めた。カメラをぶら下げて浅草や日本橋を歩いたり、休みには赤津の郷里・信州へスキーに出かけたりもした。
大学のゼミでは一ノ瀬が新聞写真研究、赤津が商業写真を専攻。目指すジャンルは違っていたが、将来の夢をお互いによく語り合ったという。
「二人ともサラリーマンになるという気持ちはまったくなくて、どうやって一流のカメラマンになるか、名を成すには人と違うことをしなければ、なんてよく話したものです」
大学卒業後、赤津はファッションカメラマンの助手となり、一ノ瀬はUPI通信社の仕事を得た。仕事は忙しく、学生時代のように頻繁に会うことはなくなったが、ときどき深夜の銭湯でばったり会い、互いの近況を話し合った。人生変えた親友の”消失”
72年1月、仕事を早く終えた赤津は久しぶりに一ノ瀬のアパートを訪ねた。一ノ瀬は「明日、行くんだ」と言って荷造りをしている最中だった。戦場への最初のステップとなるバングラデシュへ旅立つ前夜だった。何を履いて行くんだ、と赤津が尋ねると一ノ瀬の指差した先には愛用の下駄!米軍の払下げ品が好きだった赤津は、折しもその日アメ横で軍用ブーツを買ってきたところだったので、一ノ瀬にそのブーツを渡したという。
その後、戦場から赤津の元へ、一ノ瀬からの手紙がたびたび届く。撮影したフィルムも届いた。赤津は仕事の合間にそれを現像し新聞社や出版社に売り込んで歩いた。
「一ノ瀬独特の体当たり的なやり方で撮った写真には並みはずれたパワーがあります。
僕にはないものがある。それを誰かに認めてほしいという気持ちは、ひとごとではなかったんです。ヤツが世に出れば僕もうれしいし、自分の成功にもなると思っていました」
一ノ瀬がインドシナに赴いて一年以上が過ぎた春の日、赤津のアパートに一ノ瀬が現れた。九州の姉の結婚式に出るための一時帰国だと言い、再び戦場へ向かうまでの日々を赤津のアパートで過ごしていた。久しぶりの再会ではあったが、一ノ瀬はあまり多くを語ろうとはしなかった。
「平和ボケした日本にずっといた僕らと、戦場で仕事を続けてきた一ノ瀬とのギャップを強く感じました」
悟りを開いているのではないかと思うほどに落ち着き、何か思い詰めたようにさえ見えたという一ノ瀬。一年以上も、人間の生き死にが日々目の前で繰り返される戦地の空気にさらされてきた彼は、危険や不安のない時間が当たり前に過ぎていく日本といま混乱のさなかにあるインドシナの状況との矛盾を肌で感じていたのだろうか。それとも、自分が求めるものへの思いを新たにしていたのか・・・。
旅立つ朝、空港へのバスに乗る一ノ瀬の思い悩むような様子に赤津は、何かやるのではと直感したという。そして、「死んだら何にもならないんだからお前絶対に死ぬなよ」と声をかけて送り出した。
それから半年あまり後、一ノ瀬が常々手紙に書いてよこした夢、アンコールワット潜入の決意を知らせる手紙が赤津に届き、一ノ瀬は消息を断った。ほぼ同時に、一ノ瀬が捕らえられたというニュースも伝えられた。赤津は芸能人や料理などの撮影をするフリーカメラマンとして独立していた。親友の身を案じた赤津は、なんとかしてあげたいと伝手を頼って国会議員を訪ねたり、署名を集めたり、カンボジア政府宛の手紙を送るなど救出のための手を尽くした。しかし、再び一ノ瀬が赤津の前に姿を現すことはなかった。
いま赤津は、アウトドアショップの社長の座にある。六十人程の従業員を抱え、東
京、名古屋、福岡に店を持つ。会社を創ったのは、ベトナム戦争が終わり、自然と人間とのふれあいが社会的に広がりはじめようとしていたころだった。それまでの登山や釣りといったレジャーが、バックパッキングとかアウトドアとかのことばで言われるようになってきた。もともと山好きだったこと、そのころ知り合った人物の影響を受けたことなどからアウトドアの世界に傾いていったのだった。
「一ノ瀬の事件があってから、写真へのこだわりがなくなってしまいました。ともに夢を語り、励まし、刺戟し合った相棒がいなくなったことで、萎びた風船のようになってしまったんです」
ともに抱いた写真の夢は、青春を過ごした親友と一緒に記憶のなかの存在となってしまった。しかし、赤津は一ノ瀬がきっとどこかにいて、いつか現れるといまも思い続けている。“自分探しの旅”だった?
日大写真学科で一ノ瀬の一学年下に写真家の横木安良夫がいる。横木の、学生時代の一ノ瀬の印象は、無口で腕っ節が強そうだが、ちょっと人懐こく、他の学生とは雰囲気の違う存在だった。同じクラブだったからか、どういう経緯からかは覚えていないが、一ノ瀬のアパートを訪ねたこともあった。しかし、日大の学園紛争が激しくなっていく中で、顔を合わせる機会は少なくなり、クラブも解散したので、一ノ瀬が卒業するころには自分とは「生きる世界が違っていた」と言う。
「当時の僕達は、やる気のないシラケ世代と言われ、学園紛争にしても政治的に明確な意識があって参加していたのではなかった。そのときの雰囲気、みんなが無関心ではいられない状況のなかで動いていたところがある。それは<私>という一人称が何かをするのではなく、いつも<僕ら>という複数形でいる意識だった」そんな横木には、先輩の一ノ瀬がインドシナの戦場に写真を撮りに出かけたことが意外に思えた。横木たちにとってジャーナリストは左翼の代名詞、ベトナム戦争に関心があるということは反戦運動や成田闘争といった左翼的な運動につながることだったからだ。いつもひとりという印象の、まるで左翼的でない一ノ瀬とベトナムとが結びつかなかったという。
大学を出、著名な写真家の助手になっていた横木は一ノ瀬が捕らえられたというニュースを聞いてはいたが、日常の忙しさのなかで身近なことには思えなかった。それが数年前、ベトナムの旧サイゴンを訪れたことで、記憶のなかの一ノ瀬が甦った。
「現地で通訳を頼んだベトナム人が僕と同世代で、実際に戦争を闘ったという話を聞きました。それで、一ノ瀬さんもそのときここにいて写真を撮っていたのかと思ったら、そのころの時代がリアルに感じられて、すごく興味を持ったんです」ロバート・キャパは好きだが、戦場カメラマンになろうとは思わなかったという横木は、独立して広告やファッションを撮影するようになる。一ノ瀬は、報道カメラマンとして何とかものになりたい、そんな気持ちを抱いて戦場に飛び込んだ。その生き方は、自分が何をしたいかを確かめるいわば「自分探しの旅」だったのではないかと横木は言う。そして、アンコールワットという自分のために撮りたい写真を求め続けた一ノ瀬の姿が、テレビやコンピューターといった擬似体験にあふれた現在に、現実味を持って受け入れられるのではないかという。
「目の前で起きていること、目の前にあるもの、その求心力から逃れられる人間はフィクションじゃないのかと思う。だから、アンコールワットを目前にしていた一ノ瀬さんにはアンコールワットしかなかったんだと思うし、そこへ向かっていったことにリアリティーを感じます」
アンコールワットに似た岩山
一ノ瀬がカンボジアで付けていた日記に「幼友だちのタケちゃん」が登場する。シアムリアップで親友となった物理の先生チェット・センクロイの友人が「タケちゃん」そっくりだったと書いている。私は、この「タケちゃん」に会ってみたいと思った。そして、一ノ瀬と一緒に過ごした子ども時代を知りたいと思った。タケちゃん=原建彦は、長崎県諫早市で高校教師をしていた。高校時代ラグビーをしていたというだけある体格で、顔立ちは、言われてみればなるほどカンボジア人のようにも見える。一ノ瀬とは高校までをともにし、別々の大学に進んでからも東京でよく会っていたという。「泰造は意志が強く、気も強かった。子どものころから自分でこうと決めたら絶対にやる男でした」
幼稚園、小学校と二人は一、二を争うガキ大将で、ケンカもしたが野山を駆け回ってよく遊んだ。それが、中学、高校と進むにつれ一ノ瀬の腕白ぶりは影をひそめる。高校時代は、その落ち着きようは原と一ノ瀬が友だちと知って「なんで」と不思議がられるほどだったという。
「泰造は成長したんでしょうね。私は、子どものままだった。高校のころから写真の道に進むと言っていました。カメラを持って歩いていて、私もよく撮ってもらいましたよ」
一ノ瀬や原が子ども時代、よく遊んだ場所のひとつが桜山だった。武雄温泉の裏手にある百メートル程度の岩山で、切立った頂上に立つことが子どもたちの目標だったという。誰が一番に岩のてっぺんに登ってヒーローになるのか、文字通りお山の大将になって武雄の街を見下ろすのはだれか。子どもたちはそんなことを競い合っていたのではなかったか。
私は一ノ瀬の子ども時代を想像しながら桜山に向かった。武雄温泉の入り口に建つ楼門から西へ登りはじめる。駐車場を過ぎて行くと道は先細り、山頂へ続くらしい参道が見えた。苔むした古い石段が真直ぐに続いている。その先には、森の木々の向こうに岩の頂が突起物のように見えていた。
その光景に、私ははっとした。一ノ瀬の写真集 「遥かなりわがアンコールワット」の表紙にあった写真を連想したからだ。青々とした森の奥に頭を突き出したアンコールワットの中央塔。私が見た桜山の光景は、まさにそれだった。そして、頂上へ向かう石段はアンコールへの道のようでもあったし、アンコールの遺跡そのものにも見えた。カンボジアのシアムリアップで、一ノ瀬は幼い日に遊んだ故郷を、アンコールワットに見ていたのではなかったか。たとえ意識の中にはなくとも、殺伐とした戦乱の日常に疲れた心の奥底に、郷里への思いが息づいていたのではなかったか。ふる里へ帰っていくように、アンコールワットへ向かったのではなかったか・・・。二百余りの石段を登りながら私はそう思った。
ベトナム、カンボジア、ラオスとインドシナの混乱期を取材したカメラマンは数多い。そのなかで、一ノ瀬泰造は体当たりで撮影した写真に加え民衆に向けた優しい眼差しを残している。そして、写真だけでなく一ノ瀬本人にまつわるエピソードの数々。その最たるものが、<アンコールに憧れアンコールに消えた男>だろう。戦場という血なまぐさい舞台に立ちながら、まっしぐらに青春を駆け抜けた、そんな鮮烈なイメージがあるのは、その人生があまりにも若くして幕を閉じたからだろうか。しかし、その軌跡は何度もわれわれの前に甦り、あの時代を、その後のインドシナを思い起こさせる。
自らの意志と身体で生きた一ノ瀬泰造の姿は、その写真とともにこれからも瑞々しくありつづけるだろう。
(敬称略)
■参考文献 ▽一ノ瀬泰造『遥かなりわがアンコールワット』(一ノ瀬泰造写真集刊
行委員会) ▽一ノ瀬泰造『地雷を踏んだらサヨウナラ』(講談社) ▽一ノ瀬清二
『一ノ瀬泰造 戦場に消えたカメラマン』(葦書房) ▽横木安良夫『サイゴンの昼
下がり』(新潮社) ▽浅田恒穂「アンコールワットに消えた青春」『地平線から1
982』(地平線会議)
早川文象プロフィール
1964年千葉県生まれ。ドキュメント写真家。92年雲仙普賢岳災害取材のため長崎県島原市に移住。被災地と人々の表情を各誌に発表。写真展「普賢の記憶」を96〜97年にかけ各地で開催。その後諫早湾干拓問題、東チモール独立問題等を取材。東京在住。
(TEL=03-3370-2540、e-mail:bunzorby@gd5.so-net.ne.jp)
この記事は東海教育研究所発行の月刊「望星」の好意により転載させていただいてます。
http://www.mind.ne.jp/bosei/ tokaiedu@mail.mind.ne.jp