��

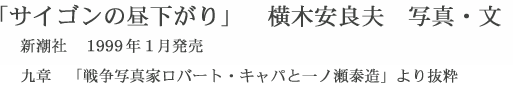
�i���j
�@1967�N4���A�l�͑�w�ɓ���ʐ^���U�����B
�@���������T�[�N���̈��y�ɁA1947�N�A���ꌧ���Y�s����̈�m���ב��������B
�@��m���͑�w���ƌ�A�t�o�h�ʐM�Г����x�ǂŃA���o�C�g������B
�@������1972�N1���Ɏ���ň�p�푈�̎�ނɗ������A�O���ɂ̓J���{�W�A�ɓ����B�X�g�����K�[�ƌĂ��ꔭ���A�t���[�̐푈�J�����}���Ƃ��ẴX�^�[�g�������B
�@�����ň�m���͊��x�ƂȂ��A�J���{�W�A�̈�ՃA���R�[�����b�g�ɐ����B�e�����݂�B���{�R�ɎB�e�t�B������v�����ꂽ��A��x�̓N���[���E���[�W���i�J���{�W�A�������j�ɕ߂܂������A������������B����6���u���{�R�ɂƂ��čD�܂����炴��W���[�i���X�g�v�Ƃ̗��R�ŃJ���{�W�A�������ދ��ɂȂ�B
�i�����j
�@�P�O�E�Q�P�̑����߂��K�p���ꂽ��A�|�S�̃t�F���X��j�ăf���������ꍞ�V�h�w�\�����B�e���A�V��v�ۂƑ�X�ؕ��ʂ���A�W�������~���̏������点��@�������A���ݓ����̍��ɂł��Ƃ��ْ͋������B��̐▽�B�߂܂�B�ӂƌ��ƐV�h�X�e�[�V�����r���̐��H����1�K�ɏ����Ȗ��肪��|�c���ƌ������B�l�̓z�[�����э~��A�K���ɂ��̏����ȑ��ɔ�э��B�����͌��O�֏��������B�֊�����z���A���������������\���A�F�����͂��܂������������B�����L��ɂł�Ƒ��b�Ԃ��R���Ă����B������B�e����l�́A������������삯���ʐ^�ƋC��肾�����B���ƂŒm��̂����A��͂��m���������悤�ɐV�h�w�\���ɂ��ĎB�e���Ă���B
�@���̐��T�Ԍ�̐[��A�o���P�[�h�������ꂽ�w�����A�֓��R�Ƌ��ɋL�����E���̏W�c���P������B���߁A���ɏ���֓��R���D�����������A���ɂȂ�Ƒ��̊w���̑S�������삯���t�P�����B����ꂽ�����̉E���i�����͊w���̑̈��̊w���B�l�Ɠ����N���X�̂r�������j�̓����`�ɂ������B
�@������A�w���̊X�́A1000�l�̋@�����ɕ�͂���×܃K�X���T���U�炳�ꂽ�B�E���̏P���Ƃ��̌��ʂ̏W�c�����`�������{���̖��ڂ������B�o���P�[�h�̂Ȃ��̖�60���́A�����ɖ����A��R���Ȃ�����S���ߕ߂��ꂽ�B
�@�l�́A�E���P���̃j���[�X���āA�w���̊X�ɗF�l�Ƌ삯�����B�@�������w�������W����l�q���A�×܃K�X�ɖڂ���炵�Ȃ���A�������ɒ��߂Ă����B�����Ńu���b�N�̃����W�t�@�C���_�[�J�����A�j�R���r�o����Ɏ���m���ב������������B���łɃT�[�N���͉��U�����̂ŁA�ނƂ̊W�͂Ȃ��Ȃ��Ă����B�l�����͖ڂ����킹�邾���ŁA���Ƃ��������Ƃ͂Ȃ������B
�@��1969�N2���A�ēx�@�������w�����͂����B�����ăo���P�[�h�͕��ӂ���A�����͊��S�ɉ������ꂽ�B
�@���̌�\�ʏ�A�w���̊X�ɕ��a���߂�A�X�ɂ͐V�����i���X��X���I�[�v�������肵���B
�@5���A��N���x�����w�����s��ꂽ�B
�@�����Ŗl�́A�O����͋C�����Ȃ��������A�����ׂ��ϖe���w���������Ă������Ƃ�m��B
�@�������A�S�~�n��3����1�̋��Z�ɂ́A�w���ɂ���Đ苒����o���P�[�h�����炳�ꂽ�B�������A�����ƍL���3����2�̕~�n�ɂ́A���݉�Ђɂ�鋭�łȍ|�S�̃o���P�[�h�A�t�F���X�������ƈȑO���炻�т��Ă����̂��B�����ł͊w�����������A�E�����o���P�[�h���P�����ċ@�������w���̊X���×܃K�X�ŐZ�������Ƃ��ł����A���Ⴍ���Ⴍ�ƍH���s���Ă����B
�@�����ăo���P�[�h�������������ƁA�w���̕~�n�S�̂ɂ����ƁA��苭�łȃt�F���X���\�z���ꂽ�̂��B���w���͂��̟B�̂Ȃ��A�t�F���X�̒��ōs���邱�ƂɂȂ����B�����̃T�[�N���͈�x�͉��U�������̂́A�㋉���������Ă��ԂƂ��������Ă����B���̂������ŁA�V�����̃I���G���e�[�V�����̌�ɁA�e�T�[�N���̊��U���A�����ꂽ�B�̂Ȃ��ł��邱�Ƃ�������Ă����B
�@���̓��̒��A�V�������U�̂��߁A�e�T�[�N���̕����S�����A�V�����Ƌ��ɁA�K�[�h�}�������d�Ƀ`�F�b�N����B�̒��ɂ��낼��Ɠo�Z�����B�܂���w���͉ߌ��h�ɂ��W�Q������Ă����̂��B
�i�����j
�@�l����w�𑲋Ƃ���9������A���钘���Ȏʐ^�Ƃ̃A�V�X�^���g�ɂȂ������傤�ǂ��̍��A���̕ւ�Ɉ�m���ב������F�g�i���ɍs�����ƕ������B
�@�ӊO�ȋC���������A�������ȂƂ��v�����B�����l�̗����ł́A����̋C�^������オ�������F�g�i���ɍs�����Ƃ́A�����I�ȍs���Ɏv���Ă����B��m���͑̈��n�̖����ȐN�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����ΊX����`����E���c�̂̂ق����������Ă���悤�Ɏv���Ă������A���������������������B
�@���������̎���A�푈�J�����}���ɂ��������̂́A�ނ̗l�ȓ��̔h�̐l�ԂȂ̂��ȂƔ[���������B�ނ͒��ȃq���[�}�j�Y���Ń��F�g�i���ɍs�����̂ł͂Ȃ��B�ނ͂��肠�܂鎩���̃G�l���M�[�U�����邽�߁A������q���邽�߂ɍs�����̂��A�Ɩl�͍l���Ă����B
�@���N�A�ނ��J���{�W�A�ōs���s���ɂȂ������A���̋~�������̘b���A�A�V�X�^���g���̖l�ɂ��������Ă����B�C�s���̖l�͎��Ԃ��܂������Ȃ��������Ƃ����邪�A���̊������A���l���̂悤�ɁA�������璭�߂Ă����B
�@1978�N�l���A�t���[�̎ʐ^�ƂɂȂ���3�N�ځA��m���ב��̏��ȂƓ��L���܂Ƃ߂��u�n����T���E�i���v�i�u�k�Њ��j���o�ł��ꂽ�B���R�e���r�ł��̃h�L�������^���[�ԑg�����������ŁA�{��ǂނ��Ƃ͂Ȃ������B�l�͂��̃e���r�̂Ȃ��́u�ב��v�ƌĂԁA�ނ̗��e�̈�m���ב��ƁA�l�̒m��u��m������v������l���Ƃ͎v���Ȃ������B�����ɂ̓i�C�[�u�ȁA��l�̑�ȑ��q�����݂��Ă����B
�i�����j
�@��m���ב��͓���̃��F�g�i���̐��ɗ��������A���܂菤�i���l�̂Ȃ��|�W�V�����ɕ�R�Ɨ����������ɈႢ�Ȃ��B��m�����J���{�W�A�̃A���R�[�����b�g�ɂ���������̂́A���̐푈�̋��S�́A���������Ăł��B�e����ΐ��E�I�X�N�[�v�ƂȂ�A���A���Ɍ����A���Ɩ��_�́A�B��̔�ʑ̂��A���R�[�����b�g����������ɈႢ�Ȃ��B�����ƈ�m���ɂƂ��ăA���R�[�����b�g��ڎw�����Ƃ͎��R�Ȃ��Ƃ������̂��낤�B
�@���J���{�W�A�́A1970�N�A�e�ĉE�h�̃����E�m�����h���̌R���N�[�f�^�[�ɂ���āA�S�y���푈�Ɉ������荞�܂ꂽ�B���F�g�i���ƈႢ1953�N�t�����X��芮�S�Ɨ������V�A�k�[�N�̉����J���{�W�A�͕\�ʏ㕽�a�ȍ��������B�A���R�[�����b�g�͐��E�I�ό��n�Ƃ��ē�����Ă����B���������F�g�i���Ɛڂ���R�x�n�т́A����R�̌R���⋋�H�A������z�[�`�~���E���[�g�ɂȂ��Ă����B�������������Ă����V�A�k�[�N�͂����ٔF�����B�A�����J�́A�D�����̌����A�z�[�`�~���E���[�g����ł��ׂ��A�J���{�W�A�̓���閧���ɔ��������Ă����B���������ʂ͌���ꂸ�J���{�W�A�ɐe�Đ������������邱�Ƃɂ���āA���F�g�i�����͂��悤�Ƃ����B
�@�Ƃ��낪�A�����J�̘��S�����A�����E�m�������ɑR����ׂ��A���F�g�i���Ƌ�������J���{�W�A�������i�N���[���E���[�W���j�́A�_�����爳�|�I�Ȏx�����A�J���{�W�A�������B�ɑ����āA�A���R�[�����b�g���苒���ėv�lj������B�ȗ��A���R�[�����b�g�͉���R�̃V���{���ƂȂ�B�@
�i�����j
�@1973�N8��17���A�T�C�S������؍��̒e��A���D�Ńv�m���y���Ɍ��������B3�������v�m���y���ɒ����Ȃ��Ƃ����댯����܂�Ȃ����[�g���B�v�m���y���㗤��A���ӂ̐퓬��R���|���`�����̍U�h�����ނ��邪�A���̂Ȃ��̓A���R�[�����b�g�����̂��Ƃ����Ȃ������B��m���͉��x�ڂ��̕��������A�悤�₭11��5���A�A���R�[�����b�g�̖�O���A�V�@�����A�b�v�ɁA�O�N�m�肠���A�ꏏ�ɕ邵���F�l�̌������̎ʐ^���B�邽�߂Ɍ��������B
�@���͈�m���͑O�N�A�A���R�[�����b�g�̈�Ղ����̓�̖ڂɏĂ����Ă���B�����1972�N3��24���B���{�R�̕ґ��p�g���[���ɂ��Ă䂭�`�����X������A�A���R�[�����b�g�܂�1.5�L���̒n�_�ɂ܂ŋ߂Â��Ă���B���������m���́A�X�Ɉ͂܂ꂽ�A�Ԃ��l�e���Ȃ��^�����ȓ��H���A�y�����ރA���R�[�����b�g�̐듃�A�������Ɖ�L�����܂ő����Ă��镗�i������B�����ň�m���̓J���[�ʐ^���ꖇ�B�e����B�����Ċ��z����L�ɋL���Ă���B
�����������U���ɗ��Č����B���̂��߂ɁA���T�C�h�ɐ����̕������ɔz�u���Ȃ���i�B�A���R�[�����b�g������ɁA�����\�X�i�C�p�[�����������Ă���Ƃ����B�]�������Y�ňꖇ�����V���b�^�[�������B�L�p�����Y�łȂ���[�܂�Ȃ��B�V�@�����A�b�v�ɖ߂�A�܂������Z������1.5� H�i��Ő��̃��u�̒���1�
H�قǐi�܂ł���B�_�A�_���b�ƈЊd�ˌ������B�u�n����T���E�i���v
�@�]�������Y�̐��E�͑��l�����B���S�ȏꏊ����`���݂鐢�E���B�L�p�����Y�͂��Ɋ��Ȃ���ΎB��Ȃ��B�ΏۂƑΓ��ɖʂƌ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ʂƌ��������Ƃɂ��A����������q�������Ƃ��ʂ��Ă���͋����ʐ^����m���͎B�肽���Ǝv���Ă����ɈႢ�Ȃ��B���̏��Z���ǂ̂��炢�������̂��͕s�����B�N���[���E���[�W���͑O�N��苭�͂ɂȂ�A�͂�肢�����������Ȃ��Ă����B
�@�J���{�W�A�̓��F�g�i���ȏ�ɍ��ׂƂ�����ꂾ�����B���łɑ�c������肩�A���F�g�i���������������̃W���[�i���X�g�������J���{�W�A�ŏ����Ă���B��m���̂悤�ɁA�g�D���o�b�N���Ȃ����t�ɂ��s���R������҂��A�P�ƂŃA���R�[�����b�g�ɐ������邱�Ƃ��������d���Ƃ��������B��������m���ɂƂ��Ă���Ȃ��Ƃ́A�킩��������Ƃ������B��Ɏ����ӎ����Ă����Ƃ��Ă��A�܂��A���Ɏ��������Ƃ���ŁA�l�Ԃǂ��ɋ��Ă����ʂƂ��͎��ʁA�Ǝv���Ă����̂��Ǝv���B
�@�w���������I�蔽��^�������ɂȂ��������ꂽ����A��m���͖���q���Đ����邱�Ƃ�]�����h���B��m���́A���E��m�邽�߁A���E�̎S��𐢂̒��ɒm�点�邽�߂ɃJ�����}���ɂȂ����̂ł͂Ȃ��B��m���͂ǂ̎���ɂł����邠���̎�҂Ɠ����悤�ɁA������m�邽�߂ɃJ�����}���ɂȂ�A���F�g�i����J���{�W�A�ɍs�����B
�@���̎����҂́A���{�̍��x�������ƃV���N�����Ă����B���ʂ̉ƒ�Ɉ�ĂΕn�����Ƃ͖����������B�����ĉ������ʂȂ��Ƃ�]�܂Ȃ���A���a�Ȑ������ł���悤�Ɏv�����B�������O�Ƃ��āA����鑤�ɂȂ邱�Ƃ��m�肷��A�y�����邹��悤�ȋC�����Ă����B�������A�����̓��Ȃ�G�l���M�[�A��S��R�₵�A���������߂悤�Ƃ���ƁA���a�ȓ��{�ɂ͉����Ȃ������B����A�Ȃɂ��������̂�������Ȃ����A�����̂���]��G�l���M�[��R�Ă����������Ǝv����҂̈�l�A��m���ב��ɂƂ��ẮA���ꂪ�ʐ^�ł���A���̂̒ꂩ�瓯�ӂł���A����q�����d���A���ꂪ�푈�ʐ^�������̂��B
�@��m���͎����̂��Ƃ��A���J�����}���A�퓬�J�����}���A�ʐ^�o�J�ƌĂ�ł����Ƃ����B�������m���́A�ނ��N��̐�y�J�����}�������Ƃ́A�ǂ�������Ă����Ǝv���B��m���̓W���[�i���X�g�Ƃ������A�l����f�r�����l�������̂�������Ȃ��B
�@1973�N11��8���B�V�@�����A�b�v�ŁA�e�F�̃J���{�W�A�l���t���b�N���[�̌��������B�e�����B�u�A�T�q�O���t�v�̂��߁A�푈�̂��Ȃ��̂ЂƂƂ��A���a�ȃt�H�g�E�X�g�[���[���B�e�����B
�@���̐�����B��m���́A�u�n����T���E�i���v�ƁA�F�l�Ɍ��t����������A11��22����23���A�A���R�[�����b�g�֒P�Ɛ��s�����܂��������B26�ɂȂ������肾�����B
�@��m����肳��ɒx��Ă����A�ʐ^�Ƃ`���́A��m���̖��O���A�ǂ��������ɏd�ˍ����Ă����̂�������Ȃ��B���̎���ł��A�ǂ̃|�W�V��������ʐ^���B�邩�Ƃ������Ƃ́A��ԏd�v�Ȃ��ƂȂ̂��B����́A�l�̓w�͂���łȂ��A����̂߂��肠�킹���B��m���͒x��ė������߂ɁA���댯�Ȏ�ނ����邱�ƂɂȂ�B�ϋɓI�ɍs�����Ȃ���ΐ��ʂ͂Ȃ��B���̌��ʂƂ��Ĉ�m���̓A���R�[�����b�g�ɏ������B��m���̖{�Ǝʐ^�W���ďC�����ʐ^�Ƃ`���́A������`�ɂ��邱�Ƃň�m������������̂��Ǝv���B�x��Ă����J�����}�����m�ʂ������������������̂�������Ȃ��B
�i�㗪�j
�I���
�S���́u�T�C�S���̒�������v��ǂ�ʼn������B
�NjL
��m���̗��e�́A�s���s��������q�̐�����M���A�J���{�W�A���{�Ɋ��x���{���̒Q�菑�𑗂葱�����B�����Ĉ�m���ב��l�������Ƃ̏��āA1982�N�A�s�a�r�̎�ނɓ��s����B�����ăA���R�[�����b�g�̖k����10�L���A�v���_�b�N�̍r���Ƃ��������̓y�ɖ��鑧�q�̈⍜�ƍĉ�邱�ƂɂȂ�B��ނɂ��ƁA��m���ב���1973�N11��22����23���A�A���R�[�����b�g�����シ���ɃN���[���E���[�W���ɕ߂܂�B�����ăv���_�b�N�ɘA�s���ꂽ�B��͑��ɍ����q���ꂽ���A���Ԃ͎��R�ɑ��l�̎B�e�������肵�Ă��炵���B���̌�A��������ȃJ���������グ���A���R�I�ȑԓx���߂��A11��28���ɏ��Y���ꂽ�B��̖̂��߂�ꂽ�ꏊ�́A���l�̑������o���Ă��āA���e�͂�����x�肩�����A�⍜�����W�����B�����A�D�ɂ܂݂ꂽ�⍜���߂��̐�ŐA䶔��ɕt�����B�⍜�̈ꕔ�̓A���R�[�����b�g�����̉��ɁA�c��͂̂��ɓ��{�Ɏ����������A���݂͌̋��A���ꌧ���Y�ɖ����Ă���B