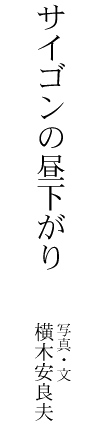ヴェトナムに行くきっかけ。
1994年アメリカがベトナム戦争以来続けていた制裁を解除した。10月、小説家矢作俊彦氏、「NAVI」編集長鈴木正文氏、アートディレクター松原健氏、BARNEYS
NEWYORKの高橋みどり氏、野性時代編集者の根本篤氏と、僕の六人はヴェトナムの土地を踏んだ。
そもそもの動機は矢作氏が「ヴェトナムへ行こう」と言ったことから始まる。
彼は1995年1月の「別冊野性時代 矢作俊彦」(角川書店)をだすにあたり、自らモデルとなる、BARNEYS NEWYORKのファッションページとタイアップした。その広告写真から、スナップ写真の全てを僕は撮影することになった。洒落たその別冊は、発売されると瞬く間に売れてしまった。
 同時に、クルマ雑誌、月刊「NAVI」の別冊「OP」の特集もヴェトナムがテーマだった。そこでも僕は、矢作氏と鈴木編集長が旅するヴェトナムを撮影した。(鈴木さんはかつて矢作氏が書いた小説、「スズキさんの休息と遍歴」(新潮社)のモデルである)
同時に、クルマ雑誌、月刊「NAVI」の別冊「OP」の特集もヴェトナムがテーマだった。そこでも僕は、矢作氏と鈴木編集長が旅するヴェトナムを撮影した。(鈴木さんはかつて矢作氏が書いた小説、「スズキさんの休息と遍歴」(新潮社)のモデルである)
「OP」という雑誌は今は休刊してしまったけれど、なかなか魅力的でユニークな雑誌だった。
僕にとって、初めてのヴェトナムは驚きの連続だった。想像のヴェトナムよりはるかにも魅力的な土地だった。
そのとき訪れた土地は、ホーチミン市とそのなかのチョロン、メコンデルタの入り口ミトー、湘南海岸のようなブンタウ、古い王宮の町フエ、かつての国境線ベンハイ川、ダナン、ヴェトナムのニースと呼べるニャチャンだ。
二度目のヴェトナムは、「PENTHOUSE」(ぶんか社)の、ヴェトナムの紹介写真だった。
タイトルは「ヴェトナムの純情」編集者は古庄 修氏、前回はアシスタント無しだったが今回は若城大介君を連れていった。
前回のアクセスは成田、香港経由、キャセイ航空でホーチミンまで飛んだが、今回は関空から、JALの直行便が飛んでいた。「サイゴンの昼下がり」のなかで、最初のページの写真(朝のチョロン)と、ニャチャンの海岸の姉妹の写真と、マリークレール校の前のダンサー、ミトーの桟橋の前の女優の写真はこのとき撮影した。
そのときヴェトナム取材には、サイゴン日本語学校で教師をした神田憲行氏が同行した。彼は、1994年潮出版より「サイゴン日本語学校始末記」で第13回「潮」賞を受賞した。
「サイゴンの昼下がり」のなかでも書いたが、日本語通訳のピンチヒッターとしてやってきたのがガイドのチュンさんだ。彼と出会うことにより、僕はヴェトナムを違った角度から見ることができるようになった。このときの撮影には、4x5(しのご)という、大型カメラを持って行った。そのカメラは鉄の箱に蛇腹がついていて、レンズをはずした状態では、素人にはカメラに見えない。H.C.M.C.の税関で、これはなにか?と質問され、いくら説明してもわかってもらえなかった。おかげで一時間以上の足止めを食らった。
二回目のヴェトナムに訪れた土地はミトー、カントー、ブンタウ、ニャチャン他。
三度目のヴェトナムは、週刊文春の原色美女図鑑の「ベトナム美女図鑑」の撮影だった。そのころには、僕はすっかりヴェトナム狂いになっていて、いたるところに、ヴェトナムに行こうと触れ回っていた。ガイドのチュンさんと知り合ったことにより、こちらの女優や、歌手や、モデルの撮影コーディネイトができることがわかり、週刊文春に売り込んだ形だ。
その撮影は、ヘアメイクとして、白川正行君を連れて行った。ヴェトナムの女性はまだ、メイクが上手でないし、どちらかというと厚化粧なので、素顔の感じを、白川君には表現してもらった。
週刊文春の編集は船越君、僕のアシスタントの若城大介君、途中まで、今は写真家のこの時は写真評論家の伴田良輔氏も、数日間同行した。
この撮影で初めて、僕はハノイを訪れた。ハノイの煉瓦工場での歌手タイン・マインさんの撮影ぐらい、暑かったことは、長い撮影人生のなかで、かつてなかった。空は薄雲に覆われ、紗がかかったような太陽光のした、気温はたぶん35、6度、しかしなんという湿度だろう。僕は顔からぽたぽたと汗をカメラに落としながら撮影した。汗でピントグラスが曇ってしい、何度も拭かなければならなかった。
この撮影で、約30人のヴェトナム美女に会う。そこでの印象は、奇麗な女性は、中国人にも、日本人にも、韓国人にも見え、美人は無国籍なんだと気がついた。ホーチミン市、ブンタウ、ハノイ、と訪れた土地は少なかったが、とてもハードな二週間の旅だった。
四回目のヴェトナムは、NUDEの撮影だった。モデルは真弓倫子嬢。この撮影は、半分ドキドキものだった。社会主義の国ヴェトナムはNUDE撮影は「NO」だからだ。それというのも、僕は友人となった通訳のチュンさんに、NUDEを撮りたいといったら、
それは絶対にできないと答えが帰ってきた。例えば娼婦などは、撮ろうとすれば撮れるが、例えば日本の雑誌はチェックされていて、顔が写ったりすれば逮捕される可能性もあるという。だったら顔をださなければ、と聞くより僕は、だったらヴェトナム人じゃなければいいの?と聞いてしまった。彼の答えは、大丈夫だろうとのことだった。
ヴェトナムにNUDE写真がまったくないわけではない。芸術としてのNUDE写真はクラシックな表現ながら存在している。僕が撮るのは、芸術写真ではないけれど、僕はヴェトナムでNUDEを撮ることにこだわっていた。ヴェトナムの光のなかに、女性を置いてみたかったのだ。このときには、英知出版の絆架氏が編集者だった。スタイリストは中村のんさん、ヘアメイクは、前回と同じ白川正行君だった。
この時の話は、「サイゴンの昼下がり」のなかでは、全く触れていない。ちょっと本の内容にそぐわないせいだ。ただ、ロケハンのときに、それまでに行けなかったところを訪れたし、ヌードを撮るために、例えばニャチャンでも、観光客が絶対行かないような場所に行ったりした。
「サイゴンの昼下がり」のなかでは、ニャチャンの海岸の波が崩れる海だけの風景の写真と赤い砂の砂丘の街、ファンティエットの写真の、それにこのときやっと、マジェスティックホテルの改装が終わり、泊まりそこで撮影した。
この撮影の究め付けのエピソードは、ニャチャンに行った時だった。ニャチャンは、ホーチミン市のような都会ではない。通訳のチュンさんは、もしトラブルが起きたときのために、友人である現役の警察官を連れてきた。彼は、チュンさんが居るときには、何も言わないが、食事のとき席をはずしたりすると突然態度が変わり、「この仕事は良くない、ヴェトナムでNUDEを撮るのは良くない、君たちは、彼の友達だから許しているが、これは特別なことだ、もし誰かに撮影を見られたりしたら、僕は君たちを逮捕する」という。
僕らは全員びびりまくった。そのことをチュンさんに言うと、彼はカタイという。でも、話しによると、かつて本田美奈子がこの地で写真集の撮影をしたとき、フィルムを没収したのは、僕だと自慢していた。
この時訪れた土地は、ホーチミン市、ミトー、ファンティエット、ニャチャン。
そして五回目に訪れたのは、1998年の6月だった。
すでに、その時には新潮社からこの本を出版することが決まっていた。
今まで、何度かヴェトナムの写真集をまとめたいと思っていたが、1994、5年のブームが一段落して、いわゆる写真集としてはまとまらなかった。あるとき僕は、ヴェトナムについての「写真」ばかりか、ヴェトナムについての「言葉」も僕のなかにたまっていたことに気がついた。僕は、この本をまとめるにあたって、文章を付けることにした。
五回目のヴェトナムは、今まで行けなかった、高原の街ダラットと、ヴェトナム一の観光地ハロン湾、毎回行っている発展目覚ましい大好きなニャチャン、二度目のフエ、ダナン、行きのがしていたファンラン、そしてもう一度確かめようと、十七度線、かつての国境ベンハイ川とその近くにあるクアンチの町。そして、ロバート・キャパの亡くなった土地、タイビン。最後に、ハノイに行った。
この旅には、ずっとチュンさんが同行した。ホテルは同じ部屋に寝た。彼の、強烈な歯ぎしりに夜は悩まされたが、楽しい二週間の男二人旅だった。
僕はそこで、今まで疑問だったことを、彼のプライベートを根掘り葉掘り聞いた。それは、いつもの僕の旅と違っていた。一番の目的が、文章を書くことだったからだ。
普段僕は、初めての土地を訪れるとき、基本的に自然に入ってくる情報以外は下調べはしない。写真を撮るにあたって、生半可な先入観を持ちたくないからだ。インタビュー写真を撮るときも、最小限の知識以外調べない。なによりも僕の個人的な第一印象が大切だからだ。会って気に入って始めてその人の著作を読んだりする。未知の土地に行くときは、ガイドブックやそれについての本は旅行カバンのなかだ。自分の目で確かめて、始めてその夜、今日見たところのガイドブックを読む。写真は理屈ではない。見回して、僕にとっての興味を切り取る作業だ。頭を空っぽにして、それを捜す。それは、五感も六感もフル動員だ。
初めてのヴェトナム、ホーチミン、サイゴンの昼下がり。僕はそうやって、「サイゴンの昼下がり」の表紙の女性に遭遇し、狩人のようにその瞬間を仕留めた。僕の興味は、「美」であり、「醜」でもあり、「愛」であり、「憎」しみ「信頼」「裏切り」であり、「新」も「旧」も「洗練」も「混沌」も「非凡」も「平凡」も、「事件」や「日常」からetc...、僕が気になるもの、だからそれは意識できることだけではなく、潜在意識や、デジャブも含めての興味だ。なんとなく匂って(臭って)くるものだ。
そういう撮影信条の僕が、文章を書くために旅をすることは、初めての経験で戸惑った。
いつものように、何も考えず撮影することはなく、意味を求めての、撮影だった。そうすることで見えてくることもあるが、かえって色々なことを見逃した旅だったかもしれない。
僕は、ヴェトナムに住んだわけではない。五回の旅を全部合計しても、二か月ちょっとの短い滞在だ。
僕はこの本でヴェトナムは何かなんて問いかけてはいない。僕が表現したことは、僕の知らなかったヴェトナムを撮影して、僕の知らなかったことを文章にしただけだ。
この本を読んで、ヴェトナムに行って見たいと思ってくれたら、うれしい。
1999年1月
その後ぼくは五回ヴェトナムを訪れている。
![]()
![]()